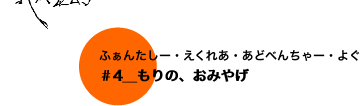 |
||||
「わからないのかい。 「君」が、彼のことを好きなんだ。いいじゃないか。 つまんない、つまんないな。 君の気持ちはだれにも分類なんかできっこないのにさ。 あいづちも待たずにいっきにまくしたてるとフォースは長いためいきをついてモズの肩から手をはなした。 このひとの笑顔は仮面のようなものなんだ。 悲しくなったモズがひとつまばたきして首を少しかたむけると、鏡にうつしたようにフォースの表情もくもった。 「ふふ、君はとっても素直なんだね。 あのさ、ぼくたちニューマンって寿命が一定してないだろ。だからさ、自分の欲求に対してとっても正直なのさ。 まあ、種族には種族なりのやりかたってのがあるんだろうがね。頭ごなしにどなってわるかったよ。ぼくは普段、大声はださないのにさ、ふふ。なんでかなぁ?」
「それで、いいのさ。それで。 |
||