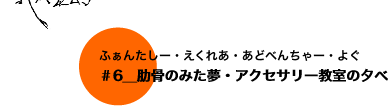 |
||||
何度もアノヒトに会ううちにやがて、たちこめていた霧は晴れそこは。 「やぁ、また会えたね。 「はい、ワタシもです。 「うんうん、そうだよ。君はレンジャーだったんだね。」 花畑に仰向けになったカノジョは切り取ったハナを顔にかざしながらワタシを見ている。 「真っ赤なんだね。好きなんだ、あたし赤い色。 空にかざしたカノジョの腕で赤いブレスレットが光を反射する。跳ね返った光がきらきらとワタシのボディをつたいおちる。不思議だ、深い赤は。非科学的だがそれはなんでもネガイを叶えてくれそうな気がする。 「どしたの、黙っちゃって。あはは、ひいちゃった?」 「いいえ、いいえ。 「このブレスから君が造られたっていうの?まるで肋骨からパートナーをつくりたもうた、ってノリかな。 わたし、君が気に入っちゃったんだけどこれはダメなんだ。あげれたらよかったんだけどね。これさ、ちっちゃい頃に父さんからもらったんだよ。」 カノジョはそっとブレスレットをほっぺたにあてた。 ダイジなモノなんだ、それは。 「お父さまに、そうですか。 「わかるよ、君はそんな子じゃないようだしね。 表情をふいに陰らせたカノジョがそこまで言いかけたとき、音が消え光が失せ、ワタシの感覚は閉ざされた。 アナタはなにを云いたかったの、どうしてそんなに悲しそうな表情を残したの?
「悲しい場面をみていたんだね、ウルト。 ワタシが外部モニターを再開するとまっさきにモンタギュー博士が視界に入った。博士はワタシの設計者だが、むやみにワタシに触れることはしない。常に心理的警戒域の外から話しかけるのだ。 「悲しみも時に美しさの要素を内包するようです。」 「そうだね。夢にも学ぶべきことはあるのさ。 普段は口数も少なくふたことみことかわすと下がってしまうウルトが珍しくその場に留まったのだ。 「博士、お願いがあります。 「ほう、なんだいそれは。」 |
||