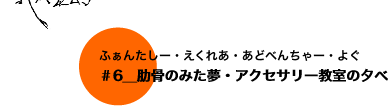 |
||||
「ごめんなさい、つきあわせてしまって。」 「いや、なぜ?いいんだ、モズ。私もヨグの事は気になっていた。君はやさしいね。 遊びに来たはものの、気もそぞろなモズを不思議に思ったハルは、事の次第を聞くとお手製のおやつの差し入れを提案したのだ。 が、それもつかのま、モズたちの家の方から聞こえてきた野太い、色気のカケラもない叫び声に今度は体温がどっと下がった。 「モズ。ジルの声じゃないか?」 「うわわ、そうみたい。なんだろう、どうしよう。」 二人は駆け出した。 「待ちなさい。」 ハルが気配もなく前に出てモズを抱きとめた。フォースならではの身のこなしに不意をつかれたモズが照れるよりもまず「なぜ?」と言うようにハルの目をみつめた。 どたどた歩き回る音。まじってかすかにヨグ姉の声。 「おちつきな、ねぇ。どうどう、ジル。」 「ごほっ、ぶっとびたくなるっちゅーかーぁぁ」 興奮しているのはヨグ姉じゃないんだ。うわ、またなんかひっくり返した。 「う、生んじゃったんだー、赤ちゃん。 沈黙、通りのむこうの短気なクラクション、また沈黙。そして。 はっはっは! それは豪放な笑い声だった。普段でもめったに声をあげて笑わないヨグ姉が笑ったのだ。 「ヤなの?ジルはー。いいじゃーない、それ。おもろいよ。 どたーん、なんか倒れるような音。 「よっし、あたしも見る。その夢。おやすみっ、ジル。」 「ん、あ、ああ。おやすみ、ヨグ姉。」 どうやらヨグ姉はその場で眠ってしまったようだ。すぐに、カチッと照明を落とす音が聞こえた。ジル姉も安心して部屋にさがったのだろう、ふう。 「おさまったようだ。」 「は、はい。あっ。」 ぼくはずっとハルの腕のなかにいたんだ。あわてて彼の腕をふりほどくと翡翠色のブレスレットがからかうように音をたてた。 「中の様子をうかがっているとき、きみの体は氷みたくカチカチだった。でも騒動がおさまるとまるで氷がとけるように変化した。 「もう、あんまり面白がらないでください。 「私の所に泊まっていけばいい。 さあ、帰ろうモズ。 強引なハルに、モズは笑顔でひとつうなづいた。
きらきら、だ。 実は、まだ真っ暗な居間にジルは立っていた。突拍子もない夢に驚いて見境無く暴れたので部屋は荒れまくりだ。じゅうたんにビーズがぶちまかれている。 けつまずいたんよねー。 それが薄いカーテンを通して入ってくるシティの光をうっすらと浴びて、きらきらと光るんだ。青いビーズが多いからまるで海みたいじゃん。 悪いけど、いわゆる美人じゃーない。髪は短くてばっさばさ、目がほそくって基本的に無表情。でもさ、不思議だけどときたまべっくらするほどキレーに見えるときがある。今もちょうどソレだな。たんなる床寝りなんだけど。 高い角度で入ってきたどこぞの車のヘッドライトの光が床のビーズに反射してしぶきをあげた。 おやすみ、よい夢を。 ヨグ。 |
||